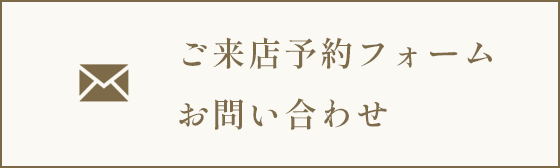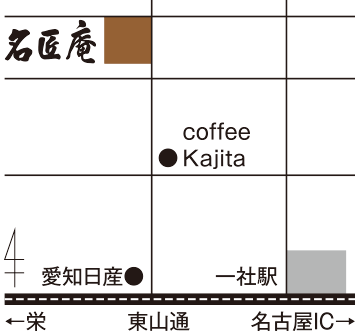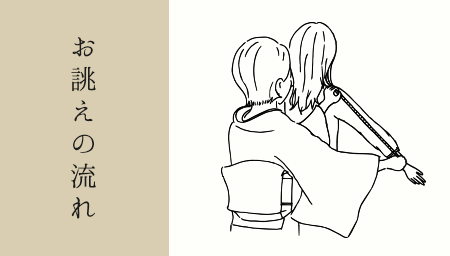江南 藤まつり
連休最終日の昨日、
愛知県江南市の曼陀羅寺 「江南 藤まつり」に行ってきました。

曼陀羅寺は14世紀後半に後醍醐天皇の勅願で建立され、
織田、豊臣、徳川家ゆかりの古文書など多くの宝物を有する尾張の名刹です。
そのお隣、曼陀羅寺公園の藤は種類も多く、
咲きぶりが見事です。
藤祭りは昨日が最終日でしたが 、
藤と共にシャクナゲやツツジ、牡丹もちょうど満開で、
なんとも華やかな光景でした。
ところで、お祭り期間中は植木市も開かれていて、
鉢植えのガクアジサイがあまりに可愛らしく
思わず購入してしまいました。

花が咲き終わったら、名匠庵の庭に植え替えしたいと思います。
藤も牡丹も紫陽花もきものの柄によく使われています。
この花の美しさをきものにうつしとりたいと思う
作家さん、職人さんの気持ちが
とてもよくわかる気がする一日でした。
初かつを
名古屋の銘菓 「初かつを」。
創業 安政元年(1854年)、
尾張名古屋の老舗菓子舗「美濃忠」さんの
期間限定の羊羹です。
名匠庵の近くにも、美濃忠平和公園店があり、
時々利用させていただいています。
はじめ、「美濃忠で初かつを買ってきて」と言われ
和菓子やさんで?カツオ??
と思ってしまいました。
で、フタを開けて納得。

上質な葛と米粉を創業以来の伝統の製法で蒸しあげた、
歯ごたえもっちりで優しい甘さのとっても美味な羊羹。
カツオのような縞模様、ほんのりした桃色を
いかに出すかが職人さんの腕の見せ所なのだとか。
本物のカツオのサクが箱に入っているようで、
見て楽しく、
さらに切り分ける時には写真の様に箱に入っている
木綿糸を使いカツオの切り身らしさを表現出来ます。

2月下旬〜5月下旬の期間限定で、
日持ちが4日ほど。
朝入荷してすぐに売り切れてしまうので
なかなか手に入りませんが
タイミング良くご来社下さったお客様に
時々ご賞味いただいています。
今年は5月25日(水)までの販売だそうで、
次は水羊羹の季節。
和菓子でも季節感を感じられる毎日です。
桜雨
週末の4月8日(土)と9日(日)は卯月名匠展を開催致しました。
ご来場くださいましたお客様、桜雨の中ありがとうございました。
名匠庵近くの平和公園の桜も今が盛り。

今朝は染井吉野と枝垂れ桜と柳の新緑と椿が一望出来ました。
本当に、、、綺麗です。
桜の花の中心のピンクが濃くなってきたら落花の気配と
言われているそうです。
この雨上がりの風でひらひら散ってしまいそうです。
ところで今年も早、四月も半ば。
新年から振り返りますと、
今年は訪問着をお探しのお客様が多い印象です。
せっかくならば良いものを、と名匠庵をお訪ねくださり、
私どもも、大変ありがたく思っております。
シンプルで上質な付下げきものも魅力的ですが、
訪問着らしい、柄や、加工がしっかり施された
華やかなきものにお客様の目が向いているような気がします。
月に一度の名匠展の開催日以外でも
ご来社くだされば訪問着をはじめ振袖、留袖、
趣味のきものもご覧いただけます。
催事などで不在の事もございますので
お電話か、メールにてお知らせください。
花開く。
肌寒い日が続いていますね。
名匠庵から車で5分程の桜の名所、
平和公園の「桜の園」の桜は、もう開花寸前です。

今日の冷たい雨が上がって気温が上昇して来たら
一気に花が開きそうです。
今年は入学式や入社式の日に満開の桜が見られそうですね。
新たなスタートの日に桜が咲いているというのは
なんだかうれしいものです。
名古屋のデパート、丸栄百貨店の「特選きもの名匠庵」も
今日から新たなスタートです。
きもの一筋50年の大先輩が昨日付で退職され、
これからは名匠庵勤続8年の女性社員を中心に運営してまいります。
きものやさんとしてこれからどんな花を咲かせるのか、楽しみです。
引き続きどうぞご愛顧下さいますようお願い申し上げます。
花束ふたつ
3月いっぱいで
名古屋の丸栄百貨店 特選きもの名匠庵を
支えて下さっていたお二人の方が退職されます。
お一人は4年間、売場で接客や事務、
商品管理など多岐にわたる仕事をこなしてくれていました。
そしてもうお一人は22年の長きに渡り
丸栄のお客様からの様々なおきもののご相談にのって下さっていました。
売場に寄せられるご相談は
冠婚葬祭のきもののご新調からお手持ちのきもののコーディネート、
寸法のお直しや染め替えなど経験や知識の必要な事柄も多くあり、
お客様のご意向を伺いつつ、気持ち良くお召し頂けるように努めて
くれていましたので、信頼して売場をお任せしておりました。
名匠庵に勤める前からの歳月をあわせれば、きもの一筋50年。
歳月をかけて積み重ねて来た知識と経験に敬意を込めて花束を、、、。

弥生名匠展から春のショールをご紹介します
名匠庵本社で本日18日(土)と明日19日(日)の二日間、
「弥生名匠展」を開催中です。
単衣のきものを特集しつつ、
同時開催で春らしいショールもご紹介しています。

ちりめんショール 長さ約174㎝ 幅64㎝
(参考上代 260,000円 税別)
こちらは 京都のメーカー「渡敬」さんのショールです。
ほんのり桜色の丹後ちりめん(絹100%)に
優しい色合いの絹糸で相良手刺繍が施されています。
背中心に向かって宝尽くしと小花の刺繍が
たっぷり刺してありますので後ろ姿が華やかです。
すこしだけ肌寒い日の、春のお出掛けにおすすめです。
ところで庭のさくらんぼの花は今が満開。

さくらんぼの花の向こうに見える梅の花の蕾も
もうすぐほころびそうです。
弥生名匠展はご来場のご予約は不要です。
どうぞお越しください。
山中温泉 無限庵
6月に百貨店や小売店の顧客様をご案内して
山中温泉で一泊二日の名匠展を開催するため、
会場とお宿の下見に行って参りました。
展示会場に選んだのは 「無限庵」

無限庵は山中温泉のこおろぎ橋のすぐ近く。
北陸の名勝史蹟、石川県指定文化財となっていて
加賀藩最高の武家書院と言われています。

こちらは大正時代に金沢から移築された書院。
この書院にきものを展示させていただく予定です。

まだ雪の残るこおろぎ橋。
6月の展示会の頃には涼しげな清流と新緑が楽しめそうです。
無限庵での名匠展のあとは
山中温泉の名旅館にお泊まりいただき、
翌日は美味しいランチや観光へご案内いたします。
ランチの場所やお宿はまだ内緒ですが、
ご参加くださったお客様にとって楽しい旅になるように
帝産トラベルのOさんと営業部長とで
あれこれプランをたてている最中です。
どんな旅になるか、楽しみです。
名古屋の衣生活
名古屋市博物館で開催中の展覧会
「採録 名古屋の衣生活 伝えたい記憶 残したい心」。
2月11日からはじまっていたのですがなかなか時間が取れず、
けれど行くならじっくり見たいと思い、
今日、平日の午前中に思い切って行ってきました。

お店で買ってきた洋服を着ている現代、
振り返って見れば
日常にきものを着るのが当たり前だった時代がありました。
展示には
その移り変わりの過程、
地域や生業に合わせて工夫された衣料、
衣を作るための機織り、糸、裁縫道具。
晴れ着や葬送の衣、
ツネギ(家の中の普段着)、
チョコチョコ(ちょっと外出用)、
ヨソイキ(改まった時に着る)、
(ツネギ、、、。久しぶりに聞きました。
展示ではウールのきものに上っ張りでした。)
などなど、どれも今となっては
「懐かしい」ものが溢れていました。
移り変わっていく時代を見てきたこの地方の方々の
お話も名古屋弁そのままでパネルで紹介されていて
とても楽しく、又、勉強になりました。

この図録、ものすごく良いです。
機織りのこと、この地方の絞り染の
解説が本当にわかりやすいです。
そして何より実際にこの時代を生きてきた方々の
知恵とユーモアに溢れたお話がたっぷり収録されています。
名古屋市博物館さん、ありがとうございますと
申し上げたい!
「採録 名古屋の衣生活 」は
名古屋市博物館で3月26日まで開催されています。
http://www.museum.city.nagoya.jp/exhibition/special/past/tenji170211.html
ぜひお出かけ下さい。
我が社の猫たち
明日2月22日は 猫の日。
ニャンニャンニャン、、、で、ねこ。なるほど。

名匠庵の玄関には招き猫の代わりに「猫のオーケストラ」の額装が。
京都のメーカー「西原」製作の塩瀬の染名古屋帯を使って作られています。

こちらは 加賀友禅作家 石田巳代治 作の訪問着「花吹雪」。
お袖と前身頃には霞に舞う桜の花びら、
左手側の後ろ身頃の裾に お行儀よくちょこんと座った猫。
手描きならではのふわふわの毛並みがなんとも可愛い猫です。
他にも、猫柄の訪問着、染帯が数点。
どれもちょっと個性的な猫たちです。

慌てて撮ったので分かりにくいのですが
時々庭をゆっくりと横切っていく名も知らぬ猫。
石田巳代治さんの猫にどことなく似ているような、、、。
今週末の2月25日・26日は「名匠展」を開催いたします。
ご来社のご予約などは不要です。
猫たちに会いにぜひお立ち寄り下さい。
春待つ訪問着
西日本では各地で記録的な大雪が観測されていますね。
名古屋でも雪が降ったり止んだりしています。
今日はお客様ご来社の予定も、外出の予定もないので事務仕事に専念しています。
社長も今日は商品を箱から出してひとつひとつ点検しています。
せっかく仕入れた商品をお客様にお使いいただくその日まで大事に大事に手入れしています。

ところで昨年仕入れた訪問着、ちょっとご覧下さい。

「染の百趣 矢野」 梅柄の訪問着
そろそろ梅の花がほころびかけるころです。
この梅の花よく見ると、、、。

細筆で 心 と書き入れてあります。
仕入れの時、「百趣矢野」の社長に言われるまで
気がつきませんでした。
心を込めて作った証ですわね。と京言葉で言われたことを
ふと思い出し、棚から出してみました。
今くらいの時期、春のはじめごろに着たい訪問着です。